前回は認定申請の具体的な手順について説明しました。
今回は認定結果が出て、介護サービスを利用するための手順について説明したいと思います。
この記事を読むメリットは3つあります。
①介護サービスを利用するまでの流れを理解できます→いざ自分や身内に介護が必要になった場合に滞りなくサービス利用につなげることができます!
②ケアマネジャーの探し方がわかります→最近はケアマネジャーも足りなくなっていますが、効率よく見つけることができます!
③介護が必要になった場合に慌てることなく対処できるようになります→慌てて飛びついて介護サービスやケアマネジャーとのミスマッチが防げます!
介護のはじまりって?
まず、介護が必要になる場面とは実際どのようなものでしょう。
多くの方が病気やケガをきっかけに身の回りのことに援助が必要となって介護サービスを利用し始めます。認知症も病気ですよね。
単純に加齢によって体力が低下したことで起きる不自由も65歳以上であれば介護保険の対象ですが、そういったケースよりも病気やケガで急激に状態が変わって必要になることのほうがイメージはつきやすいと思います。
何が言いたいかというと、『介護が必要になる前段として病院にかかっている状態が必ずある』ということなんです。通院にしろ、入院にしろ、必ず医療のフェーズを経て介護のフェーズに移行していくんです。互いに連動しつつグラデーションで移行していきますが、弊社では『医療の出口が介護の入り口』と言っています。
具体的にはどんな風なの?
例えば、「朝起きたら脳梗塞を発症していた!半身が動かない!」とか、「転んで骨折してしまった!立ち上がることもできない!」としても、そこからいきなり「急いで介護サービス利用しないと!!」とはならないんです。まずは救急車で病院ですよね。何なら治療の結果、日常生活に影響の出るような後遺症は残らない場合も結構あります。
多くの方は、この治療の期間に介護申請をなさいます。つまり時間的な猶予があるということです。介護申請は一刻を争わなくていいんです。救急搬送されるような大きな病院(専門的に言うと急性期病院と言います)には必ず社会福祉士の国家資格を持ったソーシャルワーカーという職種の人が配置されています。その人と相談しながら介護申請ができるんです。
さすがに認知症の人が、その症状だけで救急搬送というのはあまり聞かないですが、それでも認知症という診断を得るために必ず医師の診察を受けているはずですので、やはりそこでも『前段として病院にかかっている』んです。
逆に言うと、介護申請をする前に医師の診察が絶対に必要だということです。前の記事にもありますが、介護申請の際に、必ず主治医の氏名と勤務している医院を記載しないといけません。主治医がいないひとは介護申請できないということです。医療と介護は決して切り離せないんです。
ここでひとつ余談ですが「最近うちのじいちゃんボケてきたな、これが認知症か」と素人判断しないことです。もし認知症を疑うような言動が出てきたら、近所の高齢者がよく行っている内科医院とか、じいちゃんがもともとかかっていた病院があれば一緒に行って診察を受けてください。
現象として認知症のような症状が出ていても、実際は内科的な病気が潜んでいて、その治療が済めば認知症のような症状が消えてしまうということも高齢者の場合は結構あるんです。また高齢者のうつ症状はしばしば認知症の症状に似ています。しかしうつであれば内服など治療で解消することが多いです。
いずれにしても、まず医療機関を経由することで時間的な余裕が生まれます。時間的余裕は即ち心の余裕です。この流れを掴むことで冒頭にある三つのメリットの①と③は無事クリアです。
ケアマネさんはいつ登場するの?
ここから、ついに懸案のケアマネジャー選びです。順番としては介護申請⇒認定調査が済んで、認定結果が届いたら、です。
これ際して、事前にユーザーが手に入れられる情報は非常に限定的で、ケアマネ事業所名、住所、電話番号…くらいなものしかないんですよね。ちなみにそれらの情報は申請した窓口でもらえます。もらえなかった場合は、その窓口の職員さんに「ケアマネ事業所の一覧をください」と言えば必ずもらえます。
インターネットで検索してもホームページがない事業所もかなり多いですし、仮にホームページがあっても上記の情報に加えて事業所の外観の写真がある、くらいが関の山なんです。
私の勤務している事業所もケアマネジャーが12名、うち5名が主任ケアマネというなかなかのハイスペックの事業所ですが、かなり情報のうすい(選択する際に判断材料になるほどの情報がない)ホームページです。
それでもありがたいことに、常に利用希望者がいて、人員体制上お断りするしかないくらいの状況です。→ホームページの充実度と評判は比例しないということです。
具体的な探し方は?
「結局どうやって探したらいいの??」というご質問に対しては、
①急性期病院にかかっている人は、そこのソーシャルワーカーさんに「いいケアマネさん知ってますか?」と聞く。
②お住いの地域にある地域包括支援センター、あるいは特別養護老人ホーム(できれば複数個所)に同じように「いいケアマネさん知ってますか?」と聞く。
③お住いの地域にあるデイサービス事業所(こちらもできれば複数個所)にも「いいケアマネさん知ってますか?」と聞く。
これをやって、複数回名前が挙がってくるケアマネさんは間違いなく『キャリア十分、人柄バッチリ』です。場合によってはローカルテレビや地元のフリーペーパーなんかに取材された経験のある人も同様の傾向があります。
お住いの地域で仕事をしているケアマネさんは、必ずその地域の事業所さんとお付き合いがあります。ケアマネさんによってケアマネジメント能力に大きな違いはないような気がしますが、コミュニケーション能力や対人関係の技術にはかなりの差があります。
横柄なケアマネさんとか、めちゃくちゃいます。変なところに拘って前に進まないケアマネさんも、めちゃくちゃいます。
そういったコミュニケーションに難があるケアマネさんは、事業所の方も『いいけケアマネさん』とは認識されていないので、上記の①~③を実施すると、そういったクセのあるケアマネさんを効率よく回避できます。
何が言いたいかというと、結局ケアマネジャー探しは口コミ情報が一番精度が高い、ということなんです。いまのところ、介護の業界はアナログなんですよね。
まとめ
介護が始まる前に、必ず医療の段階があります。その段階のうちに介護申請を済ませてしまい、同時進行で情報収集を進めていきます。
関係者に聞き取りをして、複数回名前が挙がってくるケアマネさんは高確率でハイスペックです。
この作業が地味で労力がかかりますが、飲食店やホテルなどと異なり、ネット上にほとんど情報がない介護事業所について情報をとるには結局アナログなものしかありません。
私も弊社や同業他社の口コミなどをネット検索しますが、良い情報も悪い情報も皆無です。専門家がさまざまな切り口、キーワードで検索して何も出ないので、おそらく一般ユーザーが検索しても何も出ません。
介護保険の利用者層のメインは高齢者なので、現状はネットに口コミを書こうという発想にならないのが理由なのかもしれません。
本日もお読みくださり、ありがとうございました。
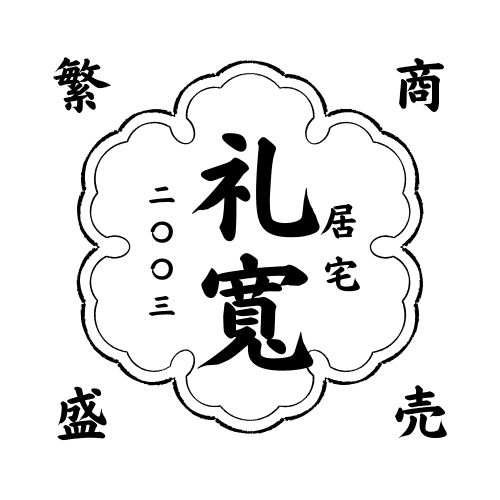


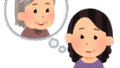
コメント