『在宅介護』と言われて一番最初に思い浮かべるのがヘルパーさんこと、ホームヘルパーではないでしょうか。法律上の正式名称は『訪問介護』です。
余談ですが私が仕事している中で、お客様から「ヘルパーさんを頼みたいんだけど」と言われたとき内心でビビってます。
お客様がやって欲しい、手伝ってほしい、と思っているものの多くが介護保険では行えないものです。
ここを上手く説明して理解してもらえないと「ケアマネが意地悪して使わせてくれない!!」という苦情になってしまうからビビッてるんです。怒られるの嫌ですから。
ちなみに訪問介護で行えない代表的なものをいくつか挙げていきますね。
・障がい者手帳や介護認定を受けていない同居人がいる場合の家事(掃除・洗濯・買い物・調理)の援助
・通院の付き添い(病院内の介助や診察の付き添い)
・草取りや窓ふきなどの、やらなくても生活に支障ない掃除(年末の大掃除含む)
・話し相手
・家族が出かけている間、付き添って援助してもらう などなど……
このあたりを期待して、「利用したい」と言ってくるお客様がほとんどなんですね。なんかやってくれそうだし、逆に「なんでダメなの?」というような内容ばかりですしね。
なので利用できないんですよ、という説明をしても納得してくれないこと結構あるんです。余談が長くなりました。
じゃあ一体何だったらやってもらえるの?と思いますよね?次は訪問介護で行える代表的なものを挙げていきますね。
・一人暮らしか、同居人が全員障がい者手帳があるか要介護認定を受けている場合の要介護者本人が使用する部分のみの掃除
・一人暮らしか、同居人が全員障がい者手帳があるか要介護認定を受けている場合の買い物、調理、本人分のみの洗濯
・要介護者本人と一緒に行う掃除、調理、洗濯などの家事援助
・自宅浴室での入浴の介助
・オムツ交換やトイレへの移動など排泄にかかわる援助
・用意されている食事を食べることそれ自体の動作の介助 などなど……
上記以外にもありますが、まあだいたい上記のいずれかが多いです。お客様の多くが期待している『家政婦を保険で雇える』というのは法律上ダメなことなんですよね。
同居している人がいたらその人にやってもらってくださいね、掃除や洗濯、買い物などの家事は仕事へ行く前や帰ってきてからできますよね、というのが法律上の考え方です。
「でも知り合いの〇〇さんの家は同居人がいるけど、来ていたヘルパーさんは掃除や買い物をしたり食事つくったりしていたらしいんだけど、あれは何だったんだ」とかも、めっちゃ言われます。
この場合は
①来ていたヘルパーさんは家事援助をしておらず、身体介護(オムツ交換や入浴介助など)をしていた
②来ていたヘルパーさんは介護保険給付ではなく、全額自己負担で利用していた
③同居している人は健康そうに見えているが、実は障がい者手帳か介護認定を受けている
④本当はダメなのに、ケアマネが故意か無知かの理由で不適切な給付をさせている
これらのどれかです。個人的な感想としては①が多いです。
あと介護保険が始まったばかりの2000年代初頭は、自治体もケアマネも制度理解が不十分だったので、今だったらダメなのにやっちゃってた、ということはあります。
こんな感じで、介護保険で行える内容の援助を『毎週〇曜日の〇時から〇分間援助する』(←これがケアプラン)という形で定期的に行うわけです。
なので、たまにある「週末に出かけるから、その間ヘルパーさんに付き添ってもらいたい、朝出て夕方には帰ってくるから」というようなお求めには対応できません。
介護保険の在宅サービスはどのサービスも基本的に『即時、随時、柔軟に』利用することはできません。以前の記事にも書いたとおり、契約と計画に基づいて行われることがルールだからです。
個人的には、訪問介護は世間一般のイメージと、実際に行っていい援助との乖離が一番大きいと思っています。やってもらいたいことのほとんどが保険ではできないことなんです。
この世間のイメージを作った人、誰なんでしょうね?おかげで私は日々ビビりながら仕事してますよ…
本日もお読みくださりありがとうございます。また次の記事もよろしくお願いします。
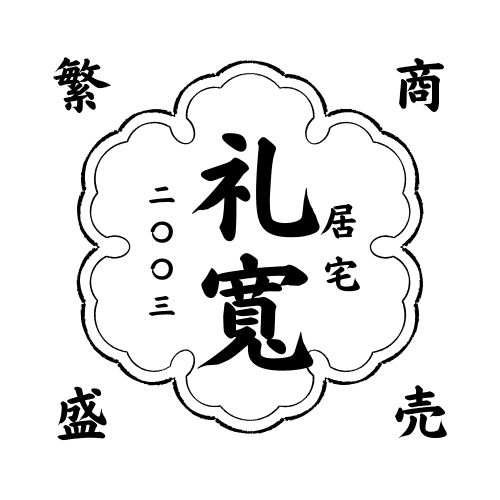



コメント