入院期間が短くなっているのは報道などでご存じの方も多いと思います。リハビリ病棟も例にもれず、退院までの日数が短くなっている傾向があります。これは病院が退院させたがっているというよりも厚生労働省の決める診療報酬による誘導であって、制度上可能ならもう少しリハビリを継続したいケースであっても退院になってしまいます。
もちろん厚生労働省もそれで充分としている訳でなく、そういった方々の退院後のリハビリの受け皿として整備されているのが『訪問リハビリ』です。
退院直後の方が利用することが多いですが、必ずしも退院直後でなければ利用できないということではなく、在宅で過ごしている中で新たなリハビリニーズが出てきた場合に導入されることもあります。
一番イメージしやすいのは、リハビリ病棟を退院した状態は、九九でいうと6の段までマスターした状態。実際に自分の家に帰って、リハビリを仕上げるのが7の段以降、という感じでしょうか。私はそんな風に説明しています。
ご自宅の環境、広さ、部屋数、段差の高さなどは、本当に十人十色なので病棟の環境でできたことが必ずしもご自宅で再現できないこともあるわけです。
そのギャップを調整するために身体機能を高めたり、逆に環境のほうを住宅改修して身体機能に合わせたりという『すり合わせ』を具体的に手伝ってくれるのが訪問リハビリというわけです。
余談ですが、病院、診療所などから提供される『訪問リハビリ』と、訪問看護ステーションから提供される『訪問看護としての訪問リハビリ』は法律上別物でありますが、今日の記事の要点はそこの議論ではないので、ひとまずその点は深めずに話を進めていきたいと思います。
訪問リハビリはその名の通り、病院にいるようなリハビリの先生(PT・OT・ST)であるリハビリ専門職がご自宅に訪問してくれます。通所でも触れましたが、柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師のようなマッサージがメインの訪問マッサージとは完全な別サービスです(病状によって、訪問リハビリであっても訓練にマッサージが含まれる場合もあります)。
そして実際に利用する方が生活する環境で、リハビリをしてくれるサービスです。
「自宅でリハビリといっても、うちはそんなに広くないし運動できるスペースなんかないよ」
↑これ、結構お客様から言われることがありますが、ご安心ください。ケアマネジャーが提案している時点で、十分訪問リハビリが提供可能なスペースがあります。
よく考えたらわかることですが、要介護認定を受けている人がやるリハビリって別に走り回ったり飛び上がったりするわけじゃないですよね。フィットネスクラブにあるような筋トレマシンを使うことも少ないです。
多くは「ベッドからトイレまでの移動を自分でやりたい」だとか、「玄関出入りと、近所のスーパーまで買い物に行くのを自分でやりたい」などの生活に密接にかかわる行為の訓練です。
もっと言えば、「ベッドからの起き上がりを自分でできるように」とか、もっとシンプルに「立ち上がれるようになりたい」とかも良くあるご希望です。
もちろんこれだけではなく、復職を目的とした訓練や、運転再開に向けての訓練なども訪問リハビリで提供した経験があります。運転の再開については経験上100パーセント、復職もかなりの割合で達成したお客様たちがいらっしゃいます。こうなってくると介護認定の更新も受けずに我々とのお付き合いを円満に終了なさいます。非常にやりがいを感じるケースです。
寝たきりに近い方から再就職を目指す方まで対応できる、実に懐の深いサービスが訪問リハビリです。
ちなみに個人的な感想ですが、私が現職についたころはあまり復職とか運転再開といった希望が実現できそうなお客様っていらっしゃらなかったんですが、ここ数年は増えてきた印象を持っています。
40代、50代の働き盛りの方の脳血管疾患の方々ですね。素人考えですが、20年前よりも医療技術が向上しているので、後遺障害が軽くなっている傾向があるのではないかと推測しています。なので現実的に復職が目指せそうな方がふえているのではないか、と。あくまでも素人の考えですので断言する根拠はないですが、肌感覚です。
訪問介護(ヘルパーさん)や訪問看護に比べて、お客様出発で利用したい、と言われることが少ないサービスですが、在宅介護の開始初期などに利用すると、のちの身体機能や介護の負荷を大きく改善させる可能性のあるサービスだと思っています。
唯一の弱点が、提供している事業者が少ないことです。山間部だとか、市街地から離れた郊外などでは利用できないことも多いです。
『年齢を重ねた人ほど、都会に住んだほうが楽だよね』というのは多くのケアマネジャーが一致して持っている見解です。
今日もお読みくださりありがとうございます。
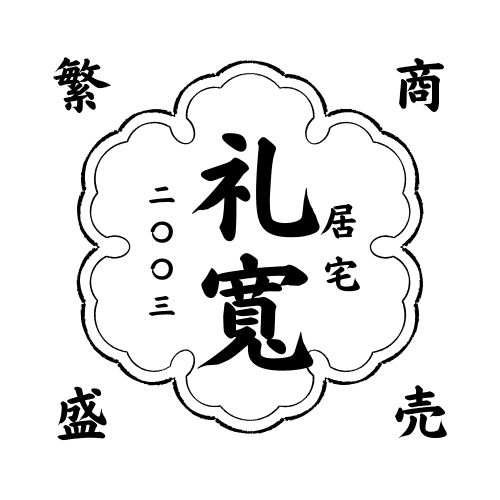

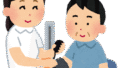

コメント