一時期、これ以外は使いたいサービスがないよ、っていうお客様からのお申込みが結構続きました。
これだけ利用したいだけだと、ケアマネさんと契約する必要がないんです。というより契約しないほうがケアマネさんにとっては都合がいいんですね。
理由は契約しているお客様の住宅改修にかかる理由書を作成しても無償で、契約していない方の理由書を作成すると一通につき2000円、自治体から報酬が払われるからです。なので、住宅改修だけがご希望の場合は、契約する意思はないことを示してくれたほうがケアマネさんは喜びます。これ豆知識です。
要介護でも要支援でも、なんらか認定されてさえいれば条件を満たす場合に住宅の改修工事に介護保険給付が受けられて、負担割合によりますが最大18万円分は給付されるというサービスです。以下で詳しく説明していきます。
住宅改修が受けられる条件
①なんらかの介護認定を受けていること
②住民票のある家に住んでいること
これが前提条件です。②は満たしていないことが結構あります。住民票はうつさないまま、ご家族の住んでいる家に同居しているパターンですね。諸手続きが大変なので住民票をそのままにしているケースはかなり多いです。
住宅改修の対象になる工事
「要介護の人の家をリフォームすれば給付金がもらえる」と単純に思い込んでいる人がかなり多いです。同じくそう思っている工務店の職人さんが、身の回りの人が要介護認定を受けたと聞きつけると小遣い稼ぎしようとして、しきりに工事をするよう勧めてくることもめちゃくちゃ多いです。
ですが、なんでもかんでも給付対象になるわけではなく、以下に示すものであって、事前審査によって自治体が認定したものだけが給付対象です。
・手すりの取り付け
・段差の解消
・扉の取り換え(開き戸を引き戸、または折れ戸に交換など)
・床や通路の材料変更(畳をフローリング、玄関外のコンクリ舗装など)
・便器の取り換え(和式から洋式のみ可、洋式から洋式は不可)
・上記の工事に付帯して必要になる工事
これらのうち、自治体が審査の結果、「そりゃ仕方ないわな」と認定してくれた場合にのみ給付されます。上の項目に該当していても、審査の結果給付されないこともあります。
このあたりは自治体によっても、担当者によってもブレがあり統一された見解みたいなものはありません。住宅改修に限らず、介護保険は自治体担当者がダメといったら基本ダメです。
とはいえ考え方として、『生命維持のためにそれをやらないと大きな支障が出る場合は許可される』という感じはあります。明文化されてはいませんが。
なので『手すりの設置』だとしても、「趣味の天体観測のために二階に上がる必要があって、その階段に手すりを設置したい」という目的だった場合は、ケアマネさんがどれだけ身体状態や介護の負担、階段昇降の危険性を理由書に記載しても、却下されます。趣味は生命維持に関係しないからですね。
なんとなく介護保険ていうと「お困りのことをお手伝いして差し上げますよ」という制度だと思っている方が多いですが、給付するかしないかを最終判断する自治体のほうでは「そうしなければ生きていられないんじゃ仕方ないから給付してやる」という感覚のほうが実態に近いです。正直優しい制度ではないです。
優しかったら介護保険ができて25年ですので、社会問題としての介護は解決しているはずよね。
ちなみに、玄関から道路までスロープになっているお宅がありますが、あれは絶対にやめたほうがいいです。
車いすの人しかいない世帯なら、あるいはいいかもしれませんが、歩く人は坂道を歩くより高さの低い階段にしたほうが安全に歩けます。
人間は坂道を安全に歩くために階段を発明しました。要介護認定をうけてからわざわざ進化を逆行する必要はないです。
階段だったら、一段一段休みながら上ることができますが、坂道の途中で休憩するのは難しいですし、雨や雪が降って、凍結していたら目も当てられません。
実際、私たちの説明を受けたうえで「スロープにしたい!」とおっしゃったお客様は、その冬に転倒して骨折なさいました。こちらはリスクとリターンについて説明しますが、それを採用するかどうかはお客様次第です。
実際の流れ
①工事内容についてケアマネさんに相談します。
②当該工事の見積もりをとります。三社くらいで相見積もりをとるべき、と私の勤務している市の介護保険課は指導しています。
③見積もりの金額に納得がいったら施工業者と契約
④本人、家族もしくは施工業者が自治体の介護保険担当窓口に出向き、申請
⑤市から許可が出たら着工
⑥完成
①~③までは人によって一週間で済む場合もあれば一か月かかる場合もあると思います。④~⑤は私が仕事をしている市では最速で2週間、長いと一か月です(市役所の担当者の忙しさに依る)。工事自体は比較的小規模なものが介護保険の対象なので一日か、かかっても二日あれば完成します。逆に言うと、その程度の簡単な工事以外は保険給付の対象ではないということです。
個人の資産である住宅をバリアフリー化して資産価値を高めることに対して保険料をつかうことは適切でないから、という理由で介護保険の住宅改修は比較的小規模な簡単な工事だけを対象としているわけです。
もちろん、自治体によっては独自施策でこれよりも使いやすいリフォーム補助を出している場合もあると思います。そのあたりは自治体の財政に依存します。
ちなみに施工業者はどこであっても制度上の問題はないので、お付き合いのある大工さんとか、知り合いの大工さんでもいいです。
がしかし、その人たちが『介護保険の住宅改修の申請』をやったことがあるかどうかは絶対に確認が必要です。下請けで施工自体はやったことがある大工さんが「やったことあるから大丈夫!」と言うこともありますが、申請までやったことはないということもあるので、よくよく確認したほうがいいです。
なぜかというと、介護保険の住宅改修の申請にかかる手続きのうち、ケアマネさんがやることは『理由書』という定まった様式のA4ペライチを書くだけなんです。それ以外の見積書や工事予定箇所の写真撮影や申請書一式は施工業者さんが作るものなんです。
これ、「全部ケアマネとかいう人がやるんだろ?」と勘違いしている大工さんがめちゃくちゃ多いんです。これまでに何人もそういう大工さんに出会いました。
写真の撮り方や、見積書の書き方に介護保険独特のルールがあって、大工さんたちが日常業務でやっている、いわゆる『大工の常識』は通用しないんです。大工さんが作った書類を預かって代わりに窓口申請したこともありますが、まったく要件に合致していない書類なので、普通に受け取ってもらえません。受け取ってもらえないということは内容の審査にすら至らないということです。
どの書類、どの写真のなにが問題で受け取ってもらえないのか、修正が必要なことは窓口担当者がきちんと説明してくれますが、それを大工さんに伝言ゲームするのって非常に効率悪いんです。
施工方法や、使用する部材の材質、見積もり金額など専門的な内容が理由でダメ出しされることが多いので、それをケアマネさんが理解して伝えるって、ちょっと考えて難しいですよね?我々はあくまでも介護保険のスペシャリストであって、建築のことなんか素人ですから。
なので、一刻も早く工事して快適な生活をしたいのに、ただでさえ一か月近く審査にかかるのに、その土俵にすら立てないという悲惨なことになってしまうんです。
「でも、それって珍しいケースでしょ?」って思いますでしょ?
私がこの仕事をしてきた中で、介護保険のレンタル業者さんの紹介でない大工さん(親戚の…とか、知り合いの…とか)で、申請できた人は一人もいません。
結局、大工さんがめんどくさくなって放り出すか、保険を使わない普通の工事としてやることになるかのどちらかですね。だいたい後者になります。ここで知り合いであるということが決め手で、「断りにくくて…」となるパターンが多いです。
まとめ
介護保険の住宅改修は、比較的小規模な工事が対象になっています。
利用するには要介護認定を受け、住民票のある家を工事する場合に対象になります。
施工業者に指定はありませんが、お勧めするのは介護保険のレンタルをやっている会社から紹介される業者を利用するほうが、うまくいく確率が高いです。
保険が利くとは言え、適正料金というものはありますので、複数社の合い見積もりを強くお勧めします。
今日もお読みくださりありがとうございます。
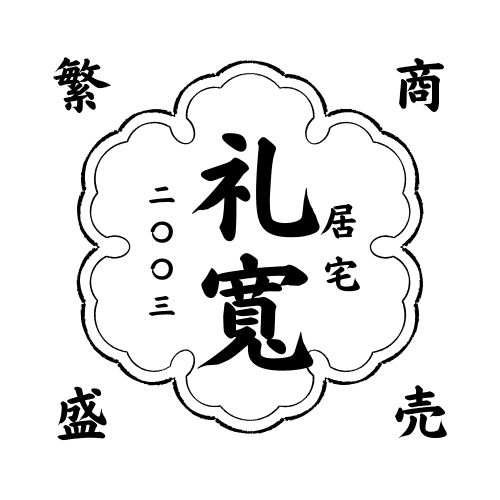



コメント